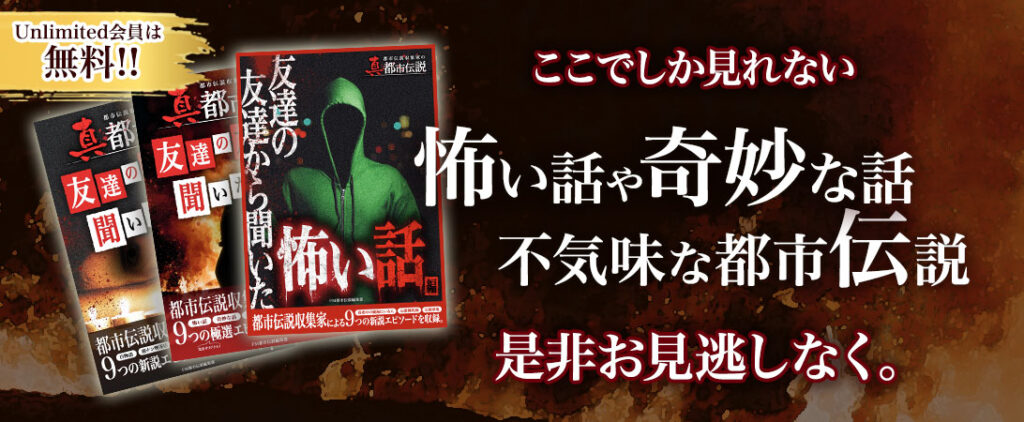【投稿者:k-14さん】
私はフランスの地方都市で、現地人の家族と暮らしています。
今回は夫・アンリが少年時代に体験した不思議な出来事を、ご紹介しようと思います。
当事者である夫から聞いた話をできるだけ詳細に再現していますが、文中では名前・地名ともに仮名を使用している事をご了承ください。
アンリは70年代生まれ、フランス中央部のV…という村で育ちました。20キロ離れた所に町があり、当時はタイヤ工場などもあって賑やかでしたが、いったんそこを出ると道路にろくな明かりもないような、そんな地方でした。
Vは四方を農地に囲まれた典型的な田舎の村で、家々が教会の周りに固まっているだけの、陸の孤島と言ってもいいくらいの所です。電車はもちろん路線バスも通らない場所で、車がないとどうにもなりません。アンリの家は、小さな村の中心からさらに離れた、はずれの所にありました。
アンリが11歳くらいの時のことです。11月1日の万聖節(日本のお盆にあたる祝日)が過ぎ、秋休みももう終わりという日でした。アンリは3歳上の兄と留守番をしていましたが、兄は休み明けのテストに向けて猛勉強をしており、ほとんど相手にしてくれない事をつまらなく思っていたようです。ふと、村の反対側に住んでいる友人の家に遊びに行こう、と思い立ちました。
「兄ちゃん、ジャンの所に行ってくる」
兄は眉をひそめました。両親は共働きで、兄弟だけで留守番をする事が多くありましたが、これは優等生である兄がしっかり弟の面倒を見てくれるもの、という親の信頼が前提にありました。一人で外に遊びに出てはいけない、と禁じられていたのです。ですが、兄はあまり深く考えずにこう言いました。
「行ってもいいけど、車道はやめとけよ。裏の農道を行けば、ジャンの家まで遠回りできるだろ。夕方ママが帰ってくる前に、必ず帰って来いよ」
当時、フランスの道路には速度制限がありませんでした。家の前の道路も、90キロ越えで飛ばしてくる車が多かったので、両親は息子たちが交通事故に遭うのを心配していたのです。
アンリは兄の古いマウンテンバイクにまたがり、庭の裏から外に出ます。家の裏手には広大な農地が広がっており、家畜用のトウモロコシや小麦が作られていました。もっとも、その時はすでに初霜が下りた後だったので、作物はすっかり刈り取られて畑は裸同然でしたが。
その道は、農地の中を長くのびていました。晩秋の灰色の空の下、舗装されていないごたごたした道を、アンリの自転車は難なく進んでいきました。友人の家までは、3キロくらいといったところでしょうか。だいたい半分くらいまで来たかなあ、と思ったところでふと辺りを見回すと、もう周囲には全く家々が見えず、ひたすら畑が広がっています。のんびりと進んでいくと、前方の畑に何人かの人影があるのに気が付きました。収穫直後のように掘り返された土の上で、腰をかがめながら作業をしている4・5人の姿が見えたのです。
アンリは自転車をとめて、その人たちに目を向けました。農耕車両や大型機器などを使って、人々が働く姿を眺めるのは、少年たちにとっては楽しいものです。ただ少し意外に思ったのは、見慣れたトラクターの姿が見えないことでした。時代は80年代後半、いくら田舎とはいえ、こんな広大な畑を素手で耕したり、収穫したりする人はいません。それだけに、アンリは好奇心にかられて、少しの間その人々がしている事に見入っていました。
彼らは長いスコップのような道具を使い、地中から何かを掘り出しては、持っていた大袋につめ、それを手押し車に積み込んでいきます。そしてよくよく見ると、人々は実におかしな恰好をしていました。11月ですから、屋外はもう相当な寒さです。現に、アンリは派手な色の防水ウインド・ブレーカーを着ていました。ところがその人たちは、白いシャツにチョッキとズボンで、頭には時代がかった帽子と、通常の農業のおじさんではありえないような恰好だったのです。また、一人女性がいるのが見えましたが、その人は畑の中だというのにロングスカート、古風な白い頭巾のようなものをかぶっていました。
アンリはますます好奇心にかられ、少しずつその変わった人たちに近づいていきました。すると、ロングスカートの女の人がふっと気づいて、こちらに歩み寄ってきます。
「若い旦那さん」と、その女性はアンリに向かって呼びかけました。
それは紛れもなくフランス語なのですが、何か違和感のある話し方でした。女性は自分の母親より若いようでしたが、日焼けをした顔にはしわが刻まれていて、なんだかおばあさんのようにも見えます。フランスの大人はこういう場合、見ず知らずの子どもに対して、「やあ君、こんなところで何してるの~?」くらいの軽い口調で話しかけてくるものです。ところがその人はアンリに対しても、何故か生真面目で、神妙な態度でした。
人見知りのアンリはびっくりしたのと、そんな妙な感覚を感じた事もあり、「ボンジュール」とも何も言い返せず、ただ突っ立っていました。
その女性は静かに、しかし厳しい調子で続けました。
「こんな所にいてはいけません。 早く、お母様の所へお帰りなさい」
それを聞いて、アンリは金縛りから急に解き放たれたように、くるりと後ろを向いて駆け出し、自転車を起こすと一目散に走りだしました。やがて、その農道に垂直に交わる別の農道を過ぎた所で恐る恐る振り返ってみると、あの不思議な人たちはいなくなっており、裸の畑が寒々と広がっているだけだったのです。
友達のジャンとしばらく遊んだ後、アンリは何となく同じ道を通っては帰りたくない、と思いました。この時は不思議な体験をしたというよりも、「あの女の人に、また叱られそうで嫌だな…」と思っただけでしたが。ともかくあの農道とはまた別の、家々の裏を通る狭い草道を通って、アンリは家に帰りました。
夕方遅く、両親が家に帰ってきた後も、この話はしませんでした。話せば一人で遊びに出たとばれてしまいますし、それを許した兄にも迷惑がかかります。ですからアンリはこの事を、長い間誰にも話すことはありませんでした。唯一話したのは、大好きな父方の祖父母です。クリスマス休暇中、一人で祖父母宅に預けられたアンリは、「この前の万聖節の休みに、こんな事があってね…」と話し出しました。
宗教的なことが大嫌いで、不思議な話を迷信として片付けるアンリの両親とは違い、祖父母は伝統的な風習や古い言い伝えを大切にする人たちでした。職人の祖父は作業の手を止めて、アンリの話に聞き入り、しばらく考え込んでからこう言いました。
「その道というのは、家の裏から伸びている一本道のことかい」
「そうだよ」
「変わった人たちがいたというのは、もう一本の道が交差するあたりだったんだね」祖母も加わります。アンリは頷きました。
「お前の話を聞いていると、その人たちはおじいさんたちが若かった頃、あの戦争があった時代の人たちのように思えるよ。いいや、もっともっと昔かもしれない。貧しい人たちが今よりもずっとずっと多くいて、収穫後の農家の畑を必死に掘り返して、小さな取りこぼしを集め、食いつないでいたんだ」
「今でもそういう人たちがいるの?」
祖父は微笑んで、首を振りました。「いないと思うよ。……お前が、たまたま昔の風景を見に行ってしまったんじゃないかな」
「アンリ。二つの道が交わる十字路というのはね、時々とんでもない事が起こってしまう不吉な場所でもあるのよ。これからはもう、一人ではあの道を通らない方がいいね。兄ちゃんに付き添ってもらいなさい」祖母も言いました。
この時初めて、アンリは自分があの日見たものの異様さをはっきり自覚しました。つまり、あの時畑で作業をしていたのは、自分とは別の時代を生きていた人たちだったのかもしれない……。そう思うと、得体の知れない恐ろしさと不安がこみあげてきたのです。それが幽霊であったのか、あるいはアンリ自身が時間を越えてしまったのかは、定かではありませんでしたが。